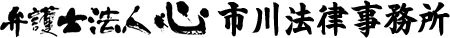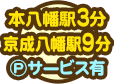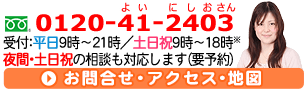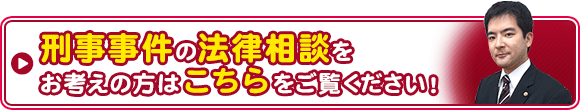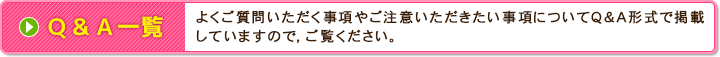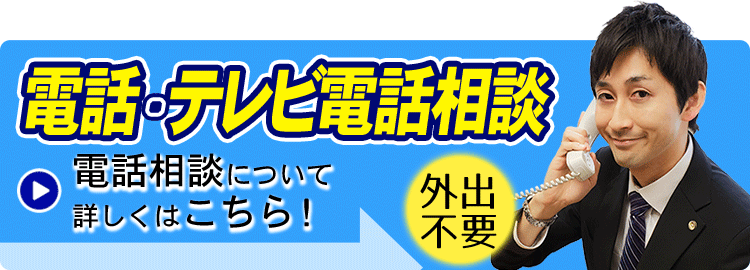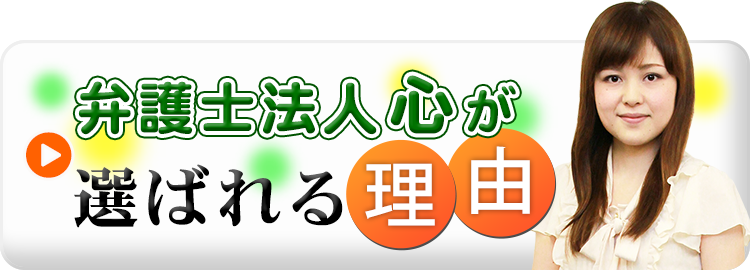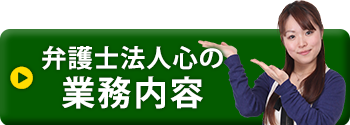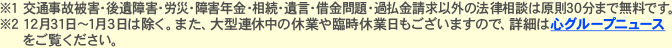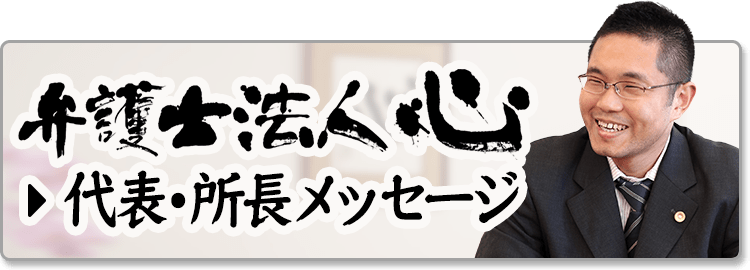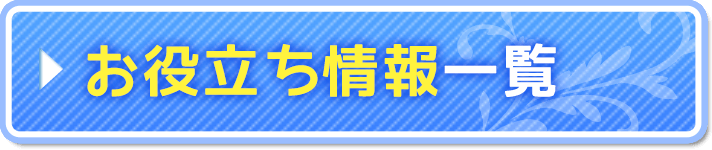逮捕されたことを会社や学校に知られたくない場合
1 会社に知られたくない場合
⑴ 逮捕されたとしても基本的には警察から会社に連絡が行くことはない
一般に、会社のお金を横領したとか、会社に事件の証拠がある、関係者がいるというような例外的な場合を除いて、警察がわざわざ会社に事件を知らせることはありません。
⑵ 在宅事件の場合
身柄拘束されず、在宅捜査を受けている被疑者の場合には、会社に知られることはほとんどないといえます。
警察や検察の取調べは平日にありますから、有給休暇などをうまく利用して休みを取れるよう調整すればよいだけです。
しかし、警察からの連絡を無視したり、忙しさからずっと出ないでいたりすると、会社へ連絡されてしまうこともありますし、場合によっては、逃亡のおそれありとして逮捕されてしまう可能性もありますので、警察や検察からの連絡にはきちんと対応することが大切です。
⑶ 身柄事件(逮捕)の場合
それでは、逮捕された場合はどうでしょうか?
逮捕された後の刑事事件の流れは以下のとおりです。
一般的には、逮捕されたとしても職場に連絡がいくことはありません。
しかしながら、逮捕勾留によって長期間の無断欠勤が続いてしまうと、クビになってしまう可能性があります。
数日ならば、家族が会社に連絡し「体調不良」で押し通せても、勾留は最大で23日間続きます。
そのため、その間ずっと「体調不良」で押し通すのはかなり困難です。
もし明確な理由を告げないまま欠勤を続けてしまうと「無断欠勤」扱いとなり、解雇事由になりえます。
無断欠勤による解雇を避けるために事情を説明しなければならならなくなると、結果的に職場に知られてしまうことになります。
逮捕されたことを会社に知られないようにするためには、短期間で釈放され、会社に行けるようにするしかない、ということになります。
⑵ 会社には連絡しないよう警察に訴える
痴漢や盗撮などが発覚して警察に連行されると、警察で取調べを受けるのですが、取調べが終わり解放されるときに、身元引受人(通常は家族)に警察へ迎えに来てもらいます。
しかし、何等かの事情で家族が迎えに来られない時には、警察は会社の上司に連絡を取って、上司に身元引受人として迎えに来てもらうことがあります。
そうすれば、会社に犯罪のことが知られてしまいますので、警察に連行されるなど取調べを受けて終わったときには、会社には絶対に連絡しないよう強く警察へ訴えましょう。
2 学校に知られたくない場合
⑴ 少年事件の流れ
逮捕された場合の少年事件の流れは以下のとおりです。
【逮捕】
逮捕は、成人と同じく72時間です。
【勾留or勾留に代わる観護措置】
勾留は、成人と同じく、原則10日、最大20日です。勾留に代わる観護措置となった場合には、10日間です。
場所は、少年鑑別所が多いですが、警察署や拘置所のこともあります。
【家裁送致】
事件が家庭裁判所に送られます。
【観護措置】
少年鑑別所に原則最大28日間、身柄拘束されます。
【審判】
審判の結果、不処分、保護処分、検察官送致(逆送致)、試験観察のいずれかになります。
試験観察になった場合には、一定期間ののち、再度審判を受けることになります。
⑵ 学校(中学・高校・大学ほか)に知られる可能性
① 警察は連絡するか
会社の場合と同じく、警察から学校に連絡するケースはそう多くありません。
学校内での犯罪、あるいは被害者も同じ生徒であるなど、学校が事件に関係していないかぎり、警察から積極的に学校に連絡することはまれです。
ただし、勾留が長引くほど学校への説明が難しくなる点は、会社への説明の場合と同様です。
② 調査官による調査
少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されると、成人の事件とは異なり、要保護性の確認のための家庭裁判所の調査官による社会調査があります。
この社会調査は、少年自身及び少年の環境の問題点を探り、なぜ少年が非行を行ったのか、再び非行を行わせないためにはどうすればよいのかを検討するためのものです。
調査官の調査結果は、家庭裁判所の審判のための大事な資料になります。
その調査のために調査官は、少年とその保護者と面談するだけではなく、必要があれば、職場の雇用主・上司、学校の教師などと面接することもあります。
そこで、調査官が学校に連絡することはありえます。
③共犯者からバレる可能性
また、少年が集団で何か事件を起こした場合、共犯は同じ学校の生徒であることは多いでしょう。
この場合、共犯の生徒やその家族、関係者などを通じて、学校に知られる可能性はあるといえるでしょう。
3 学校や会社に知られないようにするためにできること
⑴ 弁護士に相談・依頼する
弁護士に相談することで、今後、どれくらい身柄拘束されるのか、どのような処分が見込まれるのかが分かり、これに対する対応を考えることができます。
逮捕後に刑事弁護を依頼される家族の方は、今後の手続の流れや処分結果に重大な関心をもちます。
そして、それと同じくらい、会社にどう説明すればいいのかに関心を持ち、弁護士に助言を求めます。
しかし、弁護士ができることは、長期の身柄拘束に対する対応くらいで、会社や学校への直接の対応は、ご家族が行うしかないのが現実です。
⑵ 弁護士にできること
① 解雇・退学を避けるためのアドバイス
会社や学校によっては、「犯罪に関与した場合、解雇・退学とする」と規則で定められている場合があります。
逮捕後の勾留を阻止して釈放を実現できる可能性も事案によってはあるため、弁護士は「勾留されるか釈放されるかがはっきりするまでは、体調不良で欠勤と伝えたらどうですか」と助言することがあります。
しかし、判断するのは被疑者本人であり家族です。
② 早期釈放への活動
体調不良といっても、休める期間には限度があります。長くなれば病名を聞かれたり、診断書の提出が必要になったりします。
大人であれば、本人が会社にいつまでも連絡せず、家族としか連絡が取れないということを不審に思われるでしょう。
逮捕されたことを学校や会社に知られないようにするには、早期釈放しかありません。
弁護士がやるべきことは、早期釈放のための取り組みということになります。
早期釈放のためにできることは、勾留請求の阻止、勾留決定の阻止、勾留決定に対する準抗告、保釈(起訴後)などですが、事案によって異なります。
③少年事件での調査官に対する対応
上記のとおり、少年事件では担当調査官からの連絡という可能性があります。
調査官からの学校への連絡を回避するため、弁護士に弁護(付添活動)を依頼して、弁護士から担当調査官に対して「学校に知られると退学の危険性がある」「退学になると加害者少年の今後の更生に悪影響をおよぼす」ことをきちんと伝えて、学校に連絡がいかないよう事前に防止するよう取り組む必要があります。
もっとも、事案によっては完全に学校への連絡を阻止できることまでは保証できません。
④不起訴・無罪だった場合の対応
逮捕・勾留が会社や学校に知られると、その事実だけで悪い印象を与えてしまい、たとえ不起訴処分や無罪になったとしても、解雇・退学となってしまう可能性もあり得ます。
もしご本人やそのご家族が「不起訴処分だった」「無罪だった」といくら説明しても、事態が改善されないようであれば、まず弁護士が検察庁に「不起訴処分告知書」を請求します。
そして、その書面にて会社や学校に対し、不起訴処分・無罪であったことをきちんと説明して、理解を得られるよう働きかけていくことで、解雇や退学を回避します。
なお、不起訴処分告知書には罪名が記載されていますので、性犯罪の場合には告知書を会社や学校に提出するかどうかよく検討されることをおすすめします。
不貞行為の回数で慰謝料の金額は変わるのか 少年事件解決の流れと弁護士依頼の重要性